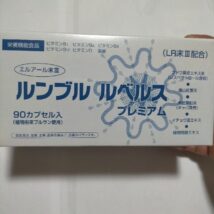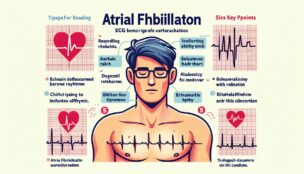血栓 赤ミミズ が選ばれる理由 を紹介。ドロドロ血液をサラサラにする成分の正体についてまとめています。赤ミミズ(学名:ルンブルクスルベルス)が血栓対策として注目されている最大の理由は、その体内に含まれる特殊な酵素「ルンブロキナーゼ」の働きにあります。
血栓 赤ミミズ が選ばれる理由
「体が重い」「血流の滞りが気になる」と感じることはありませんか。血液がドロドロになり、血栓ができやすくなる状態は、現代人にとって見過ごせない課題です。
そうした中で注目されているのが、赤ミミズに含まれる成分です。一見意外に思われがちですが、赤ミミズの体内には、血液の流れに関わる重要な働きを持つ成分が含まれています。
本記事では、赤ミミズ特有の酵素ルンブロキナーゼに着目し、従来の血流サポート成分との違いや、血栓にどのように作用するのかを分かりやすく解説します。
赤ミミズ(学名:ルンブルクスルベルス)が血栓対策として注目されている最大の理由は、その体内に含まれる特殊な酵素「ルンブロキナーゼ」の働きにあります。
この成分は、血液をドロドロにする原因物質を直接分解するだけでなく、体が本来持っている「血栓を溶かす力」をサポートするという、二重のメカニズムを持っています。
1. 成分の正体:ルンブロキナーゼ
赤ミミズから発見された「ルンブロキナーゼ」は、タンパク質を分解する強力な酵素の総称です。宮崎医科大学(当時)の美原恒博士によって発見され、長年の研究により以下の特徴が明らかになっています。
- フィブリンを直接分解します
血栓の主な構成成分である「フィブリン(血液を固めるタンパク質)」をピンポイントで溶かす性質があります。 - 副作用のリスクが低い(選択的溶解)
医療現場で使用される血栓溶解剤とは異なり、健康な血管壁などを傷つけず、血栓そのものに対して特異的に働くため、出血リスクが低いとされています。 - 経口摂取が可能です
タンパク分解酵素でありながら、胃酸などの消化液で壊されにくく、腸から吸収されて血液中に届くという、極めて珍しい性質を持っています。
2. 赤ミミズが選ばれる3つの理由
- ① 「できてしまった血栓」にアプローチできるため
一般的な「血液サラサラ成分」の多くは、血液を固まりにくくする(予防)がメインです。しかし、赤ミミズの酵素はすでにできてしまった血流の詰まり(フィブリン塊)を直接掃除する力がある点が、最大の強みと言えます。 - ② 体の自浄作用を活性化するため
単に自ら溶かすだけでなく、血管の内皮細胞から放出される物質を増やし、体が本来持っている「血栓を溶かすシステム(線溶系)」そのものを活性化させます。 - ③ 血小板の凝集を抑えるため
血栓ができる最初のステップである「血小板のベタつき」を抑制する働きも確認されており、血流をスムーズに保つ効果が期待されています。
3. 注意点と活用法
赤ミミズ由来のサプリメントは、ドロドロ血液による循環不全(肩こり、冷え、しびれなど)や、血管年齢が気になる方に選ばれています。
【ご注意ください】
すでにワーファリンなどの抗凝固薬を処方されている場合は、作用が重なりすぎてしまう可能性があります。取り入れる際は、必ず事前に主治医へご相談ください。