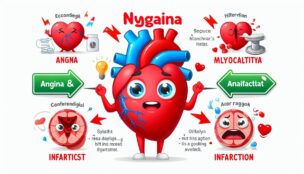狭心症 種類 は、労作時に起こるタイプと安静時でも起こるタイプがあります。タイプ別に症状や特徴を紹介します。
狭心症 種類 典型的な症状は胸痛
狭心症は、心臓の筋肉(心筋)に血液が十分に供給されず、酸素不足に陥ることで胸の痛みや圧迫感などの症状が現れる病気です。この症状が出るタイミングによって、大きく以下の2つのタイプに分けられます。
狭心症では、胸の中央部が締めつけられる、あるいは何かを押しつけられているような圧迫感を感じます。
痛みは、左肩・腕やあごまで広がり、ときには左の奥歯やみぞおちのあたりが痛むこともあります。痛みの場所は境界がはっきりしません。
「ここだけが痛い」と指で示せるような場合は、狭心症の可能性は低いといっていいでしょう。症状の持続時間は致10秒から数分で、30分とか1時間以上も続くことはありません。息切れや呼吸困難として自覚されることもありますが、これが狭心症による場合は、かなり重症である可能性があります。
労作時に起こるタイプと安静時でも起こるタイプがある
狭心症には冠動脈の動脈硬化が原因で起こるタイプと、冠動脈のけいれんが原因で起こるタイプがあります。
労作性狭心症
冠動脈硬化のために血液の通り道が狭くなつていると、運動や緊張など何らかのきっかけで、心臓がふだん以上に酸素を必要としたときに、その供給が間に合わなくなることがあります。
心筋が酸欠状態になり胸痛が起こりますが、このように何らかの労作や緊張をきっかけにして起こる狭心症を、労作性狭心症といいます。きっかけとしては、
- 急ぎ足で歩いた
- 階段や坂道を登った
- ひどく興奮した
- たばこを吸った
- 食事をした
などがあります。
ほかにも、重いものをいきなり持ち上げたり、急激に冷たい空気にさらされたときなどにも、発作が起こることがあります。
また、悪条件が重なる、たとえば、会議中にイライラしてたばこを立て続けに吸い、興奮して立ち上がったときに、強い胸痛に襲われたという人もいます。川崎病の後遺症や、大動脈弁膜症が原因で起こることもあります。
血管撃縮性狭心症
冠動脈が勝手にけいれんして縮んでしまうと、冠動脈に一時的に動脈硬化と同じような詰まりが生じて発作が起こることがあります。
これを血管撃縮(=スパスム)性狭心症といいます。血管内皮に何らかの異常が起こっていて、自律神経系の異常が起こつたときなどに引き起こされるのではないかといわれています。
これは日本人に多く、深夜や明け方の就寝中など安静時に起こるため、安静時狭心症とか異型狭心症といわれます。
労作性狭心症が心筋の酸素の需要が増えるとき起こるのに対して、安静時狭心症は一方的に酸素供給が減ることで起こります。
血管撃縮性狭心症の中には、労作で攣縮が誘発されるタイプもあります。また、冠動脈狭窄があり、それに加えて冠撃縮が起こる場合もあります。このタイプは、とくに日本人に多いようです。
心筋梗塞への移行が心配な不安定狭心症
狭心症は病状によって、安定狭心症と不安定狭心症に区別されます。
安定狭心症
狭心症の患者さんのなかには、どの程度の動作あるいは緊張によって発作が起こるのか、経験でわかっている人がいます。
たとえば、毎朝いつもの駅で階段を上がりきったところで症状が出て、2~3分休むと治ってしまう、というような発作です。
これは安定狭心症といわれ、発作が起こっても、安静にしたり、薬を使うと症状が治まります。このタイプの人の血管の内部を調べると、動脈硬化のために内腔が狭くなってはいても、プラークが右H灰化して硬く破れにくくなっていることが多いのです。定期的な検査は必要ですが、急に心筋梗塞に移行する可能性は比較的低いといわれています。
不安定狭心症
新しく出てきた労作性狭心症や安静時狭心症、あるいはいままで安定型であっても発作の回数が増えたり症状が強くなる、あるいは長引くようになったものは、不安定狭心症と診断されます。
ニトログリセリンが効きにくくなったり、静かにしていても発作が起こるタイプも不安定狭心症です。このタイプの人の冠動脈の内部を観察すると、血液の通り道が狭くなっているほか、プラークが出崩れやすい状態になっています。
血栓を作りやすかったり、血管のけいれんも起こりやすくなっている可能性があります。不安定狭心症は、プラークが崩れたり血栓となつて、血管を詰まらせる可能性があります。心筋梗塞の前兆ともいえるタイプです。
約3分の1が心筋梗塞に移行するといわれ、危険な急性冠症候群の一つに数えられています。このため、入院して、心筋梗塞と同じような管理が必要となります。
糖尿病、高齢患者では気づかないこともある
狭心症の発作の中には、1分くらい軽い胸痛があってもU、すぐに治まって、それと気がつかない場合もあります。
高齢者や糖尿病のある人では、痛みの感覚が低下していて気づかない例も少なくありません(無痛性虚血性心疾患)。
痛みがないからといって、病気が軽いわけではありません。症状がない分、無理をしたり、発見が遅れるなど、危険率が逆に高くなります。
とくに、糖尿病は全身の血管に動脈硬化を引き起こす病気です。虚血性心臓病になると、予後はよくありません。自覚症状に頼らず、冠動脈のチェックをしておくことが欠かせません。